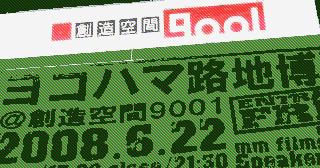 6月22日(日)、旧桜木町駅舎「創造空間9001」にて『ヨコハマ路地博'08』が開催されました。その名前からは内容が想像できない『ヨコハマ路地博'08』とはどんなイベントだったのか。今回はその様子をレポートします。
6月22日(日)、旧桜木町駅舎「創造空間9001」にて『ヨコハマ路地博'08』が開催されました。その名前からは内容が想像できない『ヨコハマ路地博'08』とはどんなイベントだったのか。今回はその様子をレポートします。
Speakers vibes(ウェアブランド)、flicker(雑誌)、mm films(BMX映像)というジャンルの異なる3団体の新作発表/販売を中心に行われる合同展示会。3団体のブース以外にも、普段親交/つながりのある ARTISTやSHOP、EVENTなどの出展ブースも設置されるので、ヨコハマを中心に活動する動きやつながりが目に見え、少なくともひとつは、新しい情報や出会いを持ち帰ることが出来るでしょう。また、当日はBMX DVD『on the low』の上映、DVD出演ライダーによるショーケース、ゆかりあるDJ/アーティストによるパフォーマンス、ライブペインティングなど、見所満載です!
以上は前回の紹介記事からの再度の引用ですが、会場では物販あり、DJあり、BMXパフォーマンスあり、ライブペイントあり・・・と、日々横浜を中心にして行われている様々な活動が会場に濃縮され、熱気に包まれていました。
会場で流されていた、mm filmsのDVD『ON THE LOW』(2008年4月リリース)のトレーラー。横浜を舞台に撮影されています。
これらの展示、物販、ライブなどが一堂に会するため、それぞれの展示等の方法も異なれば時間的なスパンも異なってきます。例えば、キムチを売る前でライブが行われ、その弾き語りの向こうでは数時間前から絵(ライブペイント)が黙々と描かれている・・・といったところでしょうか。それぞれの個性とそれらのミックス具合が印象的でした。
これらのインディペンデント的な個々の活動は、興味を持たないでいると普段はなかなか目にすることのないものでしょう。それが桜木町駅を降りてすぐの、しかも横浜市の関わる施設である「創造空間9001」で行われたことには、多くの人の目に付くというだけではなく、意外性を持って受け入れられたのではないでしょうか。
そうした、今回のイベントの開催に至る経緯や意図などに関する話は、今回の路地博'08に併せて参加団体の1つflickerによって発行された"POST-IT! vol.01"での主催者らによる座談会の中で語られています。その一部を紹介します。
「ある部分のヨコハマ」ってのは確実に紹介出来ると思うんだ。それがしかもイベンター的な寄せ集めの「ある部分」じゃなくてさ、それぞれの団体だったりお店、 DJなりが人間的に顔を合わせてつながってるっていう範囲の「ある部分」をさ。そういうのを知ってもらえたり、見て感じてもらえたり、活用してもらえたり、今後参加、交じっていくきっかけになれたらいいよね。("POST-IT!" ヨコハマ路地博'08開催記念号 vol.01より)
また、会場で配られた当日用のフライヤーには、今回のイベントに関係したお店や活動の場,横浜のBMXスポットなどが記された『ハマ路地MAP 08』が掲載されています。個々の活動が地図上で並列に可視化された様子は、上述の"POST-IT!"で語られているように、活動への参加や交流を促す仕掛けとしても捉えられるように思われます。(※試しにその地図を以下のGoogleマップ上に移してみました)
----
参考
ヨコハマ路地博'08 公式サイト






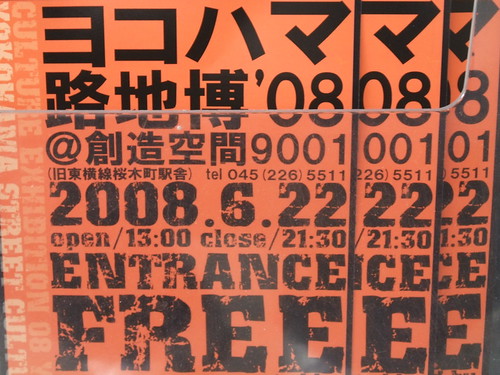






![新港地区4街区 [1]](http://farm4.static.flickr.com/3272/2568817341_2367d9442c.jpg)
![新港地区4街区 [4]](http://farm4.static.flickr.com/3117/2568641016_191bdf31ab.jpg)
![新港地区4街区 [3]](http://farm4.static.flickr.com/3049/2569593744_185cca4bf4.jpg)
![新港地区4街区 [2]](http://farm4.static.flickr.com/3193/2569607930_2f2641a738.jpg)
![みなとみらい 28街区 [1]](http://farm4.static.flickr.com/3132/2568464674_7d54219999.jpg)
![みなとみらい 28街区 [3]](http://farm4.static.flickr.com/3034/2567732051_c385c33e60.jpg)
![みなとみらい 28街区 [4]](http://farm4.static.flickr.com/3079/2568574680_5dfd23fe03.jpg)
![みなとみらい 28街区 [5]](http://farm4.static.flickr.com/3129/2568613370_260c355c76.jpg)
![みなとみらい 28街区 [6]](http://farm4.static.flickr.com/3097/2568625204_b2633182a5.jpg)
![みなとみらい 28街区 [2]](http://farm4.static.flickr.com/3001/2568532964_90a92e7fae.jpg)









